
医療業界でも問題となっている人口の地域偏在を特集した番組を見ました。
日々の買い物や教育、勤務先の数など、日々の生活の利便性を考えると、
都市部での生活を選択することは当然の流れとも言えます。
長年人手不足に悩む医療業界においても、その流れは同じです。
では、今地方都市はどのような取組で人口増を果たしているのか?
それを具体的に取り上げていた番組を拝見して、大変興味を持ちました。
私自身、子供が手を離れ、かつ定年退職をしたら、
漠然と「地方都市で自然を満喫できる生活をしてみたいな」と
思ったことは何度もあります。
ただ、実際には体が動きにくくなると、
ケアスタッフや往診に来てもらうといった医療提供を受けたり、
日常品の買い物の不安について考えなければなりません。
今回の番組では、
都市部への日々の通勤での特急券代支給や自宅の増改築等にかかる費用等の補助など、
「住みやすさの提供」というキーワードで
公共費を使用しての人口増の取り組みを取り上げており、非常に興味を持ちました。
医師招聘では、年収をUPして呼びかけをされているケースは昔から多いですが、
その他にも住宅費用や転居費用の補助を医療機関側で検討いただくケースはありました。
ただ、住宅を提供をするだけではなかなか難しく、
買い物の不便さなどから生活環境に馴染めず、
結局は退職をされてしまうといったケースもあり、
様々な面で医療機関側は改革を必要としていると感じていました。
また、そのような場面で、
地方自治体が公的病院だけではなく、地方の民間病院へも協力体制を築いて、
医師や医療スタッフの招聘に一緒になってチームとして取り組むことができれば、
環境を変えて頑張ってみたいという医師を招聘できるチャンスは増えるのでは?とも思いますが、
現状は各医療機関の経営者の個別の努力での人材確保しか手立てがないという状況です。
一方で、番組内では、
周産期医療に取り組んでいるクリニックがあるエリアで、
その地域の議員に当選を果たした女性が、
子育て世代へのバックアップをする政策を本格化させているシーンがありました。
男性議員しかいない近隣の市町村の産婦人科クリニックとの
疲弊具合の違いが印象的でした。
地域の皆さんに欠かせない医療分野については、
やはり官民一体となって取り組みなどを考えるべきだと思います。
医師の偏在については厚生労働省が呼びかけるだけではなく、
地方自治に関わる一人ひとりが現実を直視し、
招聘に尽力してもらいたいと心から思いました。


教育学部卒業後、語学関係の企業へ。「もっと人の転機に貢献できる仕事がしたい」と転職。産休を2回取得し家では怪獣(子供)の相手をしながら、アドバイザーとして奮闘中。

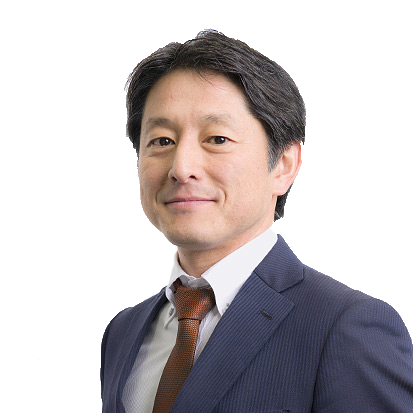 小俣 光信
小俣 光信 
 衣笠 敬広
衣笠 敬広 
 古埜 紗也香
古埜 紗也香 
 古埜 紗也香
古埜 紗也香 
 楠瀬 泉
楠瀬 泉 
 加納 由理
加納 由理 
 古埜 紗也香
古埜 紗也香 
 八木橋 辰夫
八木橋 辰夫 
 山ノ内 綾乃
山ノ内 綾乃 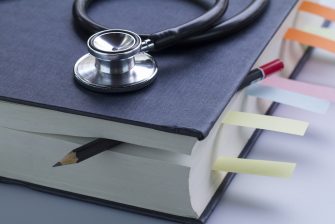
 山ノ内 綾乃
山ノ内 綾乃